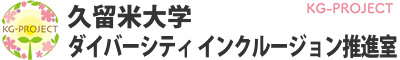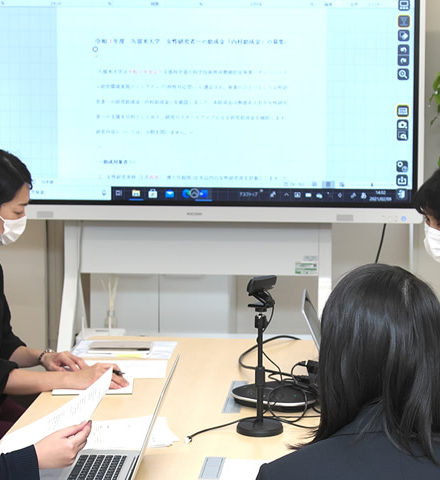運営委員からのメッセージ
Management committee message

運営委員からのメッセージ
 |
感謝と敬意の気持ちでDI推進を!運営委員会副委員長・大学病院副院長・医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座教授 梅野博仁 私は学生時代を含めると、久留米大学に40年お世話になって参りました。その間、大学組織での年齢とキャリアによる上下や子弟関係、多職種間の相互関係、性別関係、教員と学生の関係等は大きく変化してきたと思います。閉鎖的な環境から良い意味でバリアフリーになりつつあります。これは、一般社会のグローバリゼーションと大学自体の運営努力がもたらした恩恵です。多種多様な考え方や価値観を受け入れ、異なる個性を組織の強みとして活用することへの意識改革が時代とともに進んだ結果と思います。しかしながら、DI推進はまだ十分とは言えません。女性が働く環境と地位向上も重要ですが、イクメンへの配慮も必要です。種々のハラスメント解消も喫緊の課題です。少し大袈裟ですが、個性の異なる各自が大学内での立場を考え、すべての人に感謝と敬意の気持ちを抱けるようになるのがDI推進活動の究極目標であり、その一助を担えればと考えています。 |
 |
性差、年齢、人種、考え方の異なった方々が補い合うことが重要医学研究科科長・医学部免疫学講座教授 溝口充志 私は22年の長きにわたり米国で研究を行っており、ダイバーシティの重要性は身をもって実感しております。多様な考えを取り入れ、臨機応変に対応する事は、医学研究ひいては臨床医学の進歩には必須不可欠であり、地域の住民の皆様、そして国民、ひいては世界の人々の健康を守れることは世界の事例をみても明らかです。一方、ダイバーシティは「女性を守るため」のものではなく、「女性の発言の場を増やし議論を活発にし、これにより透明性も担保し、ひいては多くの女性リーダーの輩出につなげる」ことが目的と信じております。性差、年齢、人種、考え方の異なった方々が活発に議論しあい、各々の長所を活用すると共に短所を補い合ってこそ、久留米大学の更なる発展があると強く信じています。このゴールのためには、女性のための環境整備が第一課題であり、全力で取り組ませて頂きます。風変わりな意見を多々述べると思いますが、これが「ダイバーシティの始まり」とご理解頂ければ幸いです。 |
価値観や文化・社会的背景など違いを認め合い医学部看護学科長 益守かづき 今年度より、ダイバーシティ・インクルージョン推進室運営委員メンバーに加えていただきました看護学科の益守です。私は、病院内で一番数の多い看護職であり、学び勤務した大学が女子大でした(学長が女性のときもありました)ので、比較的働く女性として守られた位置にいたのだと思います。その中において、看護学生の背景の多様性や世論の女子大へのニーズの変容に伴う共学化への移行は、今振り返るとダイバーシティ・インクルージョンを検討する機会だったのではないかと思い出されます。価値観や文化・社会的背景など違いを認め合いながら、相互に作用しながら、組織としてかつ個人としてお互いを高められるような基盤が強く求められているのだと思います。私自身もDI推進に向けて学び行動し、微力ではありますが運営委員の一人として努めていきます。 |
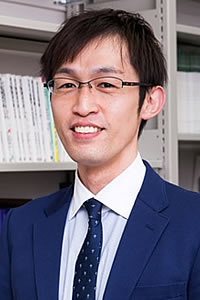 |
本学研究者のウェル・ビーイング向上に貢献したい文学部心理学科・准教授 浅野良輔 ダイバーシティ・インクルージョン推進室運営委員として、女性研究者や若手研究者の現状を心理学、特に社会心理学の観点から考えていきます。私はこれまで、性別や年齢を問わずさまざまなメンバーと共同研究を行ってきました。社会心理学では、偏見・差別に関する研究が伝統的に多く、ダイバーシティの重要性をたびたび実感してきたためかもしれません。性別や年齢(そして、学歴、職階、人種など)に関係なく、あらゆる研究者は論文や書籍の出版を通じて研究力・教育力を磨き続ける必要があります。研究機関には、研究者が研究しやすい設備、時間、システムの提供とともに、業務遂行を円滑にするスタッフの雇用・育成が求められるでしょう。ダイバーシティを実現するためには、組織全体の包括的な取り組みが不可欠といえます。ダイバーシティを促進ないしは阻害する要因の解明に向けた計画立案も視野に入れつつ、本学研究者のウェル・ビーイング向上に貢献したいです。 |
 |
ダイバーシティは女性の数を増やすこと?運営委員会委員長特別補佐・DI推進室副室長・学長直属・准教授 守屋普久子 「ダイバーシティは、女性の数を増やすのが目的ではありません。視点の多様化を目指すことが目的です」この言葉は、KG-PROJECTのキックオフ講演会で講師を勤めた、株式会社イー・ウーマンの佐々木かをりさんの言葉です。視点の多様化を図るために、物事を諮る場へ多様な人の意見を取り入れること、その結果が上位職への女性の登用につながるという内容で、とても腑に落ちました。 |
 |
多様な人材が正当に評価されることの一助を担えるように医学部内科学講座(心臓・血管内科部門)准教授 深水亜子 私は、医師として未熟な時期に出産を理由に離職し、育児期に復職した経験があります。復職の動機は、純粋に「医師であり続けたい」という思いと「医学への未練」でした。様々な葛藤と闘いながら、育児と仕事の両立の鍵のひとつといえる、自らのモチベーションを支えたものは、研究との出会いでした。研究を通じて、限られた時間の中で、目標を設定し取り組むことを学び、医師として組織や社会に貢献できることを実感することができました。さらに得られた研究成果は、学会や論文を通して正当に評価されるため、その評価が次のモチベーションを生みます。 |
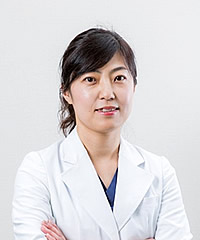 |
私ができることから取り組んでいきたい医学部内科学講座(心臓・血管内科部門)・高度救命救急センター CCU 講師 大塚 麻樹 この度DI推進室運営委員を拝命いたしました大塚です。ダイバーシティインクルージョンと言う言葉を初めて聞いたのはもう10年以上前になるでしょうか。お恥ずかしながらどこのシティ(市)かしらと思ったほどに無知でした。私が医師になった頃は、男女平等という考え方が主流でしたがよく考えてみたらそもそも異なる性が同一であるはずもなく、ダイバーシティという言葉の方がしっくりくると感じています。年齢・性別・人種と人にはたくさんの属性がありますが、その属性の違いを互いに認めあい高め合うことができなければ成熟した社会とは言えないでしょう。これから久留米大学が発展するために運営委員の一員として私ができることから取り組んでいきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。 |
 |
お互いを認め尊重しあえる安心安全な場を創りたい医学部解剖学講座(肉眼・臨床解剖部門) 講師 田平陽子 私は、ダイバーシティ・インクルージョン(DI)推進委員を経て、2022年度よりDI推進運営委員を拝命いたしました。DI推進事業の1つである女性研究者の研究力向上のためのWGにDI推進委員として活動を始め、最初は「DIとはなんだろう」と思いながらプロジェクトに参加しました。その活動において、DIを学ぶと同時に経験することができました。さらに、DI推進運営委員になり、運営委員会の皆様のご意見を通して久留米大学はDIを推進し、女性研究者はもちろん多様な人材を活躍できる場にしていきたいという思いがあると感じました。 |
 |
本学におけるダイバーシティインクルージョンの最適化を学校法人久留米大学 参与 安陪等思 出産後の女性医師が復帰するための方策を考える「元気プロジェクト」にはスタートから係わってきました.教室では病院からの支援が始まる前から色々と試みてきました.でも,実はダイバーシティインクルージョンとはなんぞやと学び始めたのは,今回のメンバーに追加されてからのことで,ほんの数ヶ月です.男女共同参画社会推進が進み,法令遵守の次のステージに進むことが求められていると思います.組織の中で個々の力量が正当に評価されること,少数意見を取り入れることが組織の発展につながることが本学の中で実現されると素晴らしいと思います.そのための検討,議論,評価の経過には透明性が高い事が求められるでしょう.思いは見えないと伝わらないのです.情報を発信するだけでなく共感者を増やすことが大切です。 |